📘 この記事は連載シリーズ
「介護者のための明日が少し楽になるヒント」の一部です。
- ▶ 第1話:すべては突然の電話から始まった ― 介護生活の入口
- ▶ 第2話:知っているだけで救われる―介護生活が楽になる制度の話(この記事)
- ▶ 第3話:介護生活に変化をもたらした介護支援専門員との出会い
- ▶ 第4話:見えない負担と向き合って ― 家族の変化が教えてくれたこと
- ▶ 第5話以降:近日公開
妻が突然倒れ、私の日常は一変しました。
仕事、慣れない家事、二人の娘の育児、そして妻の介護… 目まぐるしい毎日の中で、正直、公的な制度のことまで考える余裕なんてありませんでした。「なんとかなるさ」「制度なんて使わなくても大丈夫だろう」そんな風に、どこか楽観的に考えていたのです。
でも、その「知らなかった」ということが、後々、私たち家族に重くのしかかってくることになるなんて、想像もしていませんでした。
1. 「知らない」ことが、私たちを苦しめた現実
妻が入院してしばらく経った頃、病院から届いた請求書の金額を見て、私は言葉を失いました。
長時間に及んだ手術費用が大きいことは分かっていましたが、それでも、わずか半月で約100万円。その後も、毎月30万円近い請求が数ヶ月続きました。
十分な貯えがあったわけではありません。親戚からの支援のお見舞金や、恥ずかしながら借入れをして、なんとか支払いを続けていました。
「何か、負担を軽くする方法があるんじゃないか…?」心のどこかでそう感じてはいても、日々の生活に追われ、調べる時間も気力も、そして頼れる人もいませんでした。
そんなある日、病院の会計窓口で、ふと「高額療養費制度」という言葉を耳にしたのです。その制度の意味を知った瞬間、これまで必死で支払い続けてきたお金の重みが、後悔とともに一気に現実味を帯びて押し寄せてきました。
2. 高額療養費制度と限度額適用認定証 ― もっと早く知りたかった…
高額療養費制度というのは、医療費の自己負担額が、ひと月(月の初めから終わりまで)で上限額を超えた場合に、その超えた金額が後から払い戻される制度です。上限額は、年齢や所得によって異なりますが、例えば私のケース(当時の年収区分)では、月の上限額は約8万円強(※注:制度は改正されることがあるため、現在の正確な情報は厚生労働省HP等でご確認ください)でした。
つまり、私は本来払う必要のない金額を、何か月も支払い続けていたのです。
さらに、「限度額適用認定証」というものを事前に申請し、病院の窓口で提示すれば、そもそも支払う金額を自己負担限度額までに抑えることができる、ということも後から知りました。
もちろん、後から申請して払い過ぎた分は戻ってきましたが、「もっと早く知っていれば、あんなにお金のことで苦しまずに済んだのに…」という思いは、今でも消えません。制度は誰にでも平等に用意されているはずなのに、それを活用できるかは「知っているか、知らないか」ただそれだけなのだと、痛感させられた出来事でした。
3. 障害年金 ― 11年後に知った、時効という壁
妻は発病から約9ヶ月後に退院しましたが、くも膜下出血の後遺症である「高次脳機能障害」により、特に新しいことを記憶するのが難しくなっていました。
さらに、手術の傷口からの感染で人工骨を入れる再手術が必要になったり、てんかん発作を繰り返したりと、入退院を繰り返す日々が続きました。その結果、知的な能力も残念ながら低下してしまい、二人の娘の母親としての役割を十分に果たすことは難しくなっていました。
それでも、同居していた義母が本当に良く支えてくれ、なんとか家族5人の生活は成り立っていました。娘たちが小学生から中学生へと成長していく姿を見守りながら、私が母親代わりにならなければ、と必死だったことを覚えています。
しかし、その頼みの綱だった義母が、2011年の夏、アルツハイマー型認知症を発症してしまったのです。追い打ちをかけるように、小学校時代からいじめに悩み、不登校ぎみだった長女が、高校進学を目前にして家を出てしまいました。将来を悲観したのかもしれません…
家庭の支えを完全に失い、妻のケアと仕事の両立に心身ともに限界を感じた私は、2012年、藁にもすがる思いで区の福祉窓口を訪ねました。そこで初めて、「障害年金を申請してみては?」というアドバイスを受けたのです。
障害年金は、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に受け取れる年金です。原則として、その病気やケガで初めて医師の診療を受けた日(初診日)から1年6ヶ月が経過した日(障害認定日)に、法令で定められた障害の状態にあれば請求できます。そして、最大で過去5年分まで遡って受給できる可能性があるのです。
しかし、私たちは妻の発病から11年もの間、申請という行動を起こしていませんでした。その結果、遡って請求できるはずだった期間のうち、5年間分は時効で受け取ることができなくなっていたのです。「もっと早く、誰かが教えてくれていたら…」「なぜ、自分で調べようとしなかったのか…」後悔の念は、深く胸に突き刺さりました。
幸い、申請の結果、妻の障害年金は1級と認定され、その後の治療費や生活費の大きな支えとなりましたが、失われた5年分の重みは決して軽くはありません。
4. 生命保険 ― 入っていれば安心? 私が陥った落とし穴
「万が一のために、生命保険には入っておかないとね」よく聞く言葉ですし、私もそう思っていました。でも、「どんな保障が、いくら必要なのか」を、あなたはちゃんと理解して保険を選んでいますか?
恥ずかしながら、私は社会保険(健康保険など)の仕組みをよく理解しないまま、付き合いのある保険会社の営業担当者に勧められるがままに終身保険に加入し、高い保険料を最近まで払い続けていました。それが結果的に、ただでさえ苦しい家計をさらに圧迫することになっていたのです。
妻は専業主婦になる際に、結婚前に加入していた生命保険を解約していました。
結婚後、将来のためにと利回りの良さで選んだ個人年金保険は、あくまで「年金」であり、入院や手術に備える医療保障はほとんど付いていませんでした。つまり、今回のケースでは「使えない保険」だったのです。
ただ、不幸中の幸いだったのは、妻がもともと血圧が高めだったこともあり、加入できる保険が限られていた中で、たまたま1年更新型の生命共済に入っていたことでした。保障内容は限定的でしたが、この共済金には入院のたびに本当に助けられました。
日本には、高額療養費制度をはじめ、実は手厚い公的な社会保障制度があります。まずは、これらの制度でどれだけカバーされるのかを理解し、それでも足りない部分を民間の保険で補う、というのが賢い備え方なのだと、私は大きな代償を払って学びました。「お金や保険の知識は、学校では教えてくれないけれど、生きていく上で本当に大切なんだ」と、今、痛感しています。
5. エピローグ:知っていれば… あなたに伝えたいこと
制度を知ることの重要性を、私は身をもって経験しました。
「知らなかった」ことは、決して罪ではありません。でも、知らなかったことで失った時間やお金、そして心の余裕は、あまりにも大きかったと感じています。
- 高額療養費制度をもっと早く知っていれば、経済的な苦労は確実に減っていたはずです。
- 最初の退院の時点で障害年金のことを知って申請していれば、もっと早く生活の安定につながっていたはずです。
- 生命保険は、言われるがままに入るのではなく、自分に必要な保障を、知識を持って選ぶべきでした。
制度は、知っている人を助けてくれます。
これから介護に向き合う方、今まさに介護の真っただ中にいる方が、私と同じような後悔や苦しみを少しでも減らせるように。そして、「知らなかった」で損をすることがないように。
私のこの経験が、あなたやあなたの大切なご家族を守るための、ほんの少しのきっかけになれば、これほど嬉しいことはありません。
関連記事
👩💼 制度について、一度確認してみませんか?
「知らなかった」で損をしないために、まずは国の公式情報を確認してみることをお勧めします。難しく感じるかもしれませんが、あなたやご家族の負担を軽くするための大切な情報です。
公的な制度を正しく理解し、活用することが、あなたとご家族の未来を支える力になりますように。
次回は、孤立しがちな介護生活に変化をもたらしてくれた「介護支援専門員(ケアマネジャー)」との出会いについてお話しします。
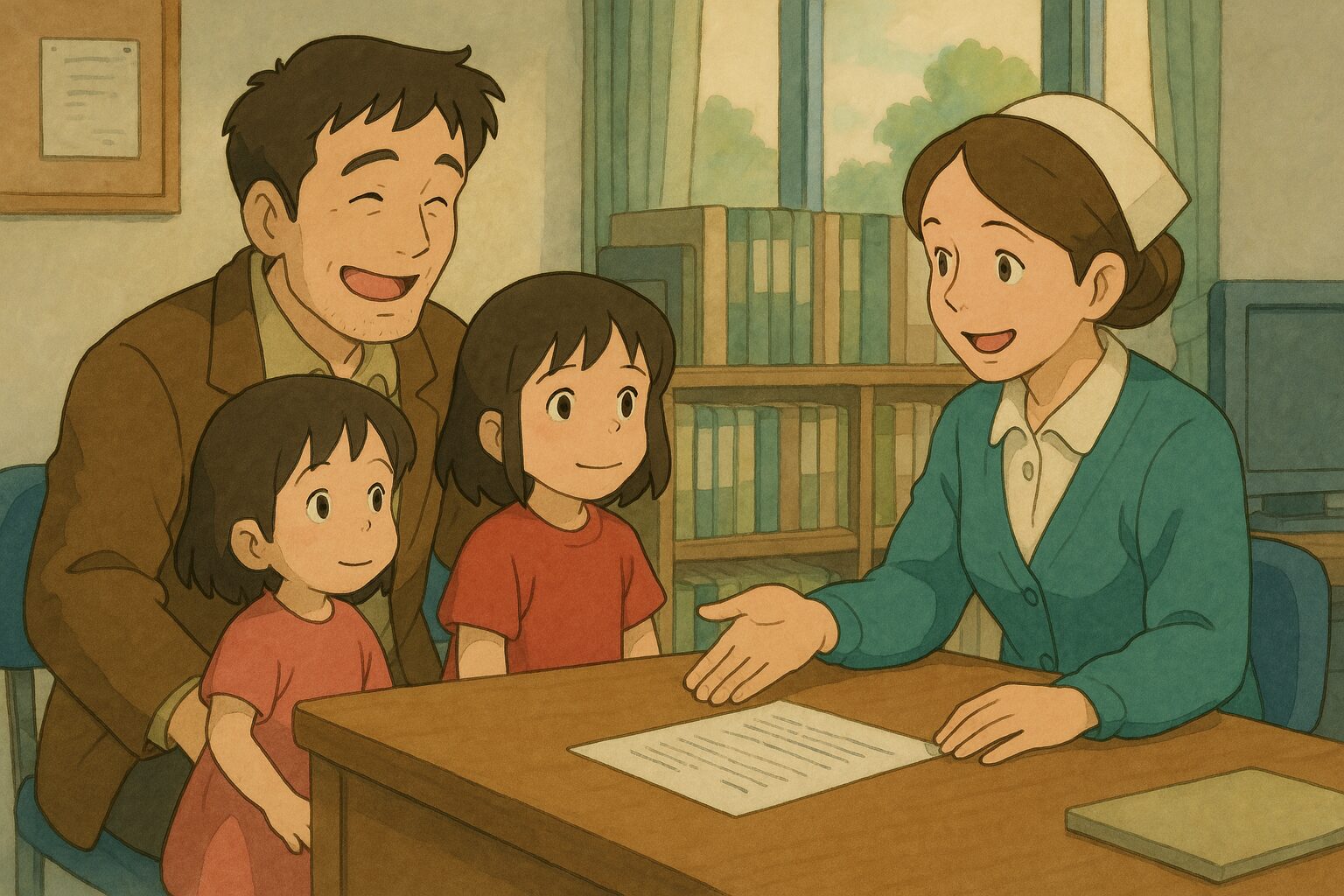



コメント