📘 この記事は連載シリーズ
「介護者のための明日が少し楽になるヒント」の一部です。
- ▶ 第1話:すべては突然の電話から始まった ― 介護生活の入口
- ▶ 第2話:知っているだけで救われる―介護生活が楽になる制度の話
- ▶ 第3話:介護生活に変化をもたらした介護支援専門員との出会い
- ▶ 第4話:見えない負担と向き合って ― 家族の変化が教えてくれたこと
- ▶ 第5話:家族の因縁と向き合って ― 母と娘に伝えたいこと(この記事)
- ▶ 第6話:(仮題)妻の発病から現在までを振り返る(準備中)
導入:20年という歳月を経て、今いる場所
妻が倒れてから、気づけば20年以上の歳月が流れていました。
長い、長い道のりでした。この連載を通して、その道のりの一部を皆さんと共有させていただいています。ここまで読んでくださった方、共感の声を寄せてくださった方に、心から感謝申し上げます。
仕事のこと、娘たちのこと、そして私を育ててくれた母のこと、もちろん妻の介護、そして自分自身のこと──。あまりにも多くの、向き合うべき存在や出来事があって、正直なところ、どこかでバランスを崩したまま、必死で走り続けてきた… そんな感覚が、今の私にはあります。
これまでの4話では、主に「介護が始まってからの家族の姿」や「介護を取り巻く環境」についてお話ししてきました。今回の第5話では、もう少し深く、“私自身の内面”、そして“世代を超えて繋がる家族の縁(えにし)”のようなものに焦点を当てて、ペンを進めてみたいと思います。少し個人的な話になりますが、これもまた、介護という経験が私にもたらした、大切な気づきの一部なのです。
1. 母が見せた変化と、私の中にあった「家族を思う心」
少し、私の生い立ちの話をさせてください。
私は、父を幼い頃に亡くし、母が女手ひとつで育ててくれた、いわゆる片親家庭で育ちました。母は再婚することなく、本当に懸命に私を育ててくれたと思います。
経済的に極端な苦労をした記憶はありませんが、思春期の頃には、母が熱心に取り組んでいた宗教活動に対して、強い反発を覚えるようになりました。「もっと自分のことを見てほしい」「まず、お母さん自身が幸せになってよ」… そんな、子どもらしい身勝手な思いを、心の内にずっと抱えていたのです。
それでも、母の中にあった「家族を大切に思う心」は、反発していたはずの私にも、知らず知らずのうちに、けれど確かに受け継がれていたのだと、今になって感じます。
妻が倒れたあの日、第1話で書いたように、連絡を受けて真っ先に病院へ駆けつけてくれたのは、同居していた義母と、そして私の母でした。その後も、遠方から気遣ってくれ、二人の孫娘たちの成長を、本当に自分のことのように喜んでくれていた母の姿を、今でも鮮明に思い出すことができます。
しかし、そんな母にも、変化は訪れました。2013年頃からだったでしょうか。少しずつ反応が鈍くなり、食事も思うように摂れなくなり… かつて私があれほど反発した宗教への関心も薄れ、医師の診断の結果、母もまた、認知症を発症してしまったのです。
幸い、近くに住む叔父(母の弟)が、本当に親身になって母のことを支えてくれました。叔父の助けもあって、母は介護認定を受け、デイサービスや訪問ヘルパーといった介護サービスを利用できるようになりました。
でも、正直に告白すると、あの頃の私は、自分の家庭のことで精一杯で、叔父への感謝の気持ちを十分に伝えられていただろうか、そして、認知症が進んでいく母の孤独や不安に、息子としてしっかり向き合えていただろうか… と、今、自問せずにはいられません。第4話で触れた、自分自身の介護への関心の低下は、妻に対してだけでなく、母に対しても、どこか同じような形で現れていたのかもしれない、と今は思うのです。
2. 母が教えてくれた「宿命」と「運命」という言葉の意味
母が元気だった頃、よく口にしていた言葉があります。
「宿命は変えられない。でも運命は、自分で切り開いていくものよ」
若い頃は、その言葉の本当の意味を深く考えることはありませんでした。でも、この20年以上の介護生活を経て、そして母自身の変化を目の当たりにして、ようやくその言葉の重みが、少しだけ理解できるようになった気がします。
私に与えられた「宿命」── それは、片親家庭で育ったこと、そして、若くして病に倒れた妻を支えながら、二人の娘を育てていくという人生だったのかもしれません。それは、誰のせいでもなく、変えようのない、受け入れるしかない現実でした。
でも、その変えられない宿命の中で、どう生きるか、何を選び取るか、どんな未来を目指すかという「運命」は、他の誰でもない、自分自身の選択と努力によって切り開いていくことができる。母は、そう伝えたかったのではないでしょうか。
そして、その想いは、今、私から娘たちへと受け継がれていきます。
特に、第4話でお話ししたように、複雑な思いを抱えて家を出てしまった長女、そして家で母のケアを担ってくれた次女には…。それぞれの人生で、もし「宿命」と感じるような困難に直面したとしても、それを乗り越え、自分自身の力で幸せな「運命」を切り拓いていってほしい。親として、心からそう願っています。今は、それぞれが新しい家庭を築き、自分の道を歩み始めてくれていることが、何よりの救いです。
3. 父として、息子として… そして、これからの私
娘たちに対しては、後悔の念も尽きません。
父親として、本当に十分な愛情を注いであげられただろうか? 妻の介護や仕事にかまけて、彼女たちの心の声に、もっと耳を傾けるべきだったのではないか? 特に、ヤングケアラーのような状況にしてしまった次女には、申し訳ない気持ちでいっぱいです。
そして、今はもう叶いませんが、母への感謝の気持ちも、もっと生前に形として伝えたかった… という心残りが、ずっと胸の奥に引っかかっています。
妻の介護は、幸いにも安定した状況が続いており、一つの大きな節目を迎えたと感じています。そんな今、私は、自分自身の「終活」ということについて、少しずつ考え始めています。
思えば、私はずっと、家族に頼ることなく、自分の力で生きていくことを是としてきました。それが「強さ」なのだと、どこかで思い込んでいたのかもしれません。
でも、これからの人生、特に老後を見据えた時、本当に必要なのは、意地を張って一人で抱え込むことではなく、誰かに「助けて」と言える勇気、そして、誰かに支えられることを素直に受け入れる心なのかもしれない、と感じ始めています。
4. エピローグ:あなたは、ひとりじゃない ― 次回に向けて
今回の第5話では、私の個人的な内面や家族との関係について、深く掘り下げてお話しさせていただきました。
介護という経験は、時に私たちに、自身の人生や家族との繋がり、そして自分自身の弱さや強さと向き合うことを迫ります。それは決して楽なことではありませんが、その過程で見えてくるものも、確かにあるのだと感じています。
私がこの連載を通して、繰り返し伝えたいメッセージは変わりません。
あなたは、決してひとりではありません。
どうか、一人で抱え込まないでください。制度を知ること、専門家に相談すること、身近な人に話を聞いてもらうこと…。ほんの少しでも、誰かに頼る、誰かと繋がる一歩を踏み出す勇気を持ってください。
このブログが、今まさに悩み、迷いながら介護という道と向き合っているあなたにとって、ほんの少しでも心を軽くするきっかけや、「自分だけじゃないんだ」と思える安心感に繋がれば、書き手として、そして同じ経験をした者として、これ以上の喜びはありません。
今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。
これまでの連載記事
- 【第1話】すべては突然の電話から始まった ― 介護生活の入口
- 【第2話】知っているだけで救われる―介護生活が楽になる制度の話
- 【第3話】介護生活に変化をもたらした介護支援専門員との出会い
- 【第4話】見えない負担と向き合って ― 家族の変化が教えてくれたこと
- ▶ 第5話:家族の因縁と向き合って ― 母と娘に伝えたいこと(この記事)
- ▶ 第6話:(仮題)妻の発病から現在までを振り返る(準備中)
💬 今回の記事を読んで
今回の第5話を読んで、あなたが感じたこと、考えたこと、もしよろしければコメント欄で教えていただけると嬉しいです。同じような経験をされた方、今まさに介護に取り組んでいる方、様々な立場からの声が集まることで、ここがさらに温かい支え合いの場になることを願っています。
次回は、第6話として、妻の発病から現在に至るまでの出来事を改めて振り返り、この20年以上の介護生活全体を通して見えてきたことなどを、お話しできればと考えています。
🌸 誰かを頼る一歩を踏み出しませんか?
介護に疲れた心を、少しでも軽くするために。
支援制度や終活サポートについて、まずは情報を集めてみませんか?
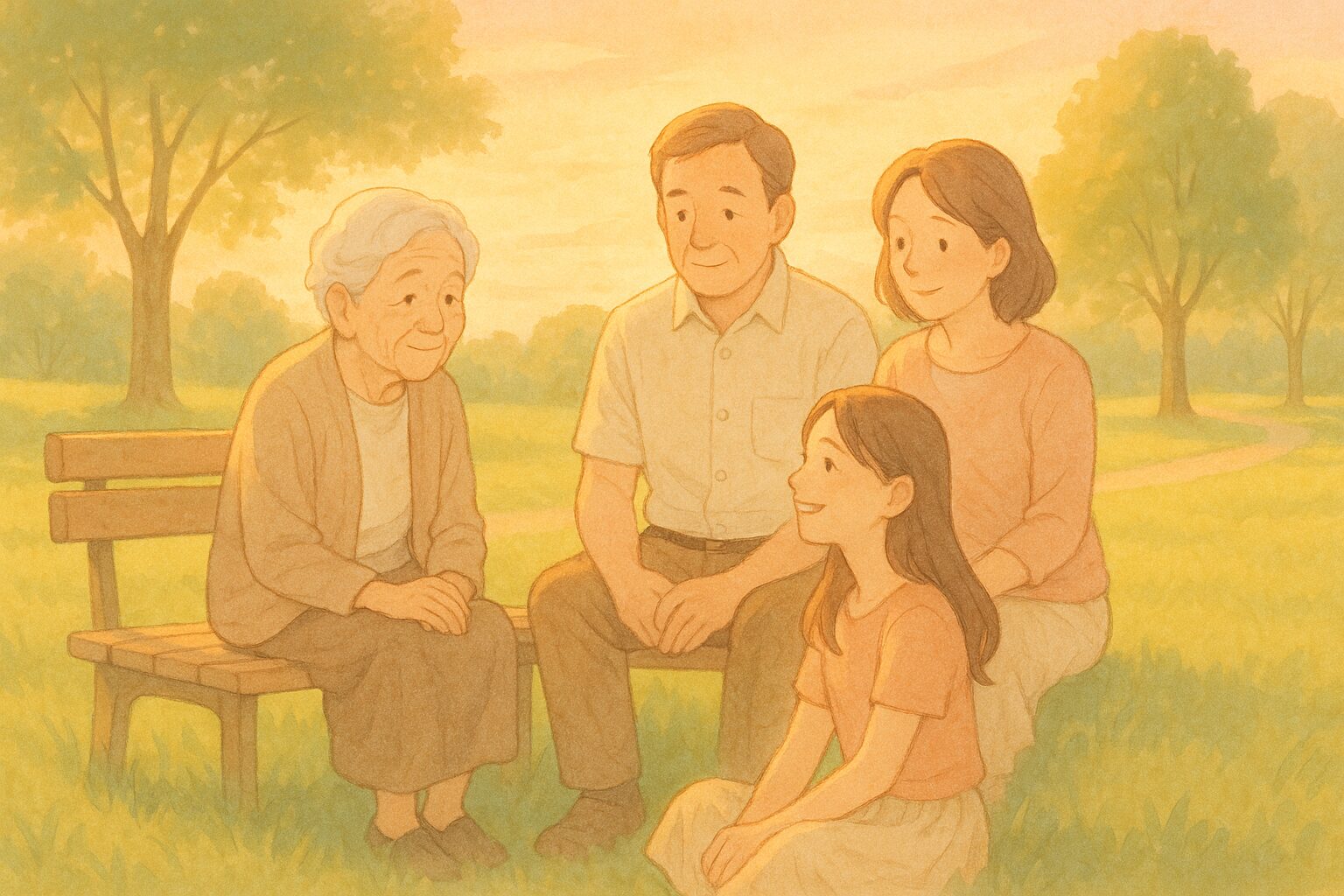


コメント