📘 この記事は連載シリーズ
「介護者のための明日が少し楽になるヒント」の一部です。
- ▶ 第1話:すべては突然の電話から始まった ― 介護生活の入口
- ▶ 第2話:知っているだけで救われる―介護生活が楽になる制度の話
- ▶ 第3話:介護生活に変化をもたらした介護支援専門員との出会い(この記事)
- ▶ 第4話:見えない負担と向き合って ― 家族の変化が教えてくれたこと
- ▶ 第5話以降:近日公開
妻がくも膜下出血で倒れたのが2002年。そして、私がどうにもならなくなって区の福祉課のドアを叩いたのが2012年。
不思議なことに、その間の10年間の記憶が、私の中ではっきりとしない部分が多いのです。記録をたどると、妻はその間に19回も入退院を繰り返していました。短い時は3日間、長い時は25日間。そのほとんどが、てんかん発作によるものでした。発作が起きると救急車を呼び、私は後から車で病院へ駆けつける… それが、いつしか日常のようになっていました。
発作が起こるパターンもなんとなく掴めるようになり、ある意味では「入院に慣れてしまっていた」のかもしれません。でも、その繰り返される発作が、妻の脳に少しずつ、しかし確実にダメージを与えていたことは、疑いようのない事実でした。
妻は高次脳機能障害によって新しいことを記憶するのが難しくなっていましたが、それでも当時は、まだ子育てに関わったり、実家に帰省したり、ご近所さんとお付き合いしたり… そんな場面もあったように思います。私の中に残っているのは、どこか「普通に暮らせていた時期もあった」という、曖昧な記憶だけなのです。
しかし、第4話で詳しくお話ししますが、長女の家出や義母の認知症発症といった出来事が重なり、家族の形は少しずつ、でも確実に不安定になっていきました。そして、いよいよ「もう自分たちだけでは無理だ」と、行政に助けを求めざるを得なくなったのです。
今回は、その2012年以降、私たちの介護生活に大きな変化をもたらしてくれた「出会い」について、お話ししたいと思います。
1. 日中の居場所づくり ― 就労支援という第一歩
福祉課との話し合いでまず決まったのは、「日中、家でただ休んでいるだけではリハビリにならない。生活リズムを整え、ご本人とご家族、双方の負担を少しでも和らげる方法を探しましょう」ということでした。
そこで、まずは介護保険サービスを利用するための要介護認定調査が行われ、妻は「要介護2」と判定されました。これを受け、夕方にヘルパーさんに来てもらえるようになり、妻も夕食の準備を手伝ったり、洗濯物をたたんだりといった、簡単な家事に参加できるようになりました。これは、小さな一歩でしたが、私たちにとっては大きな変化でした。
さらに、福祉課の方から「高次脳機能障害を持つ方が、通所しながら生活リズムや体力を整え、社会参加を目指す施設がありますよ」と紹介されたのが、「就労継続支援B型」の事業所でした。「社会的リハビリをしながら『働く』ことを目標にしてみませんか?」という提案を受け、面接を経て、2013年の夏から妻はその事業所に通い始めました。週に5日、牛乳パックをリサイクルした紙すき製品を作る作業に取り組むことになったのです。
しかし、現実は厳しいものでした。妻はてんかん発作を抑えるために、朝晩たくさんの薬を服用していました。その影響もあってか、なかなか集中力が続かず、作業の途中で横になってしまうことも多かった、と後から聞きました。
社会復帰は、やはり難しいのかもしれない…。そんな現実を突きつけられた気がしました。「もし、もっと早く、発病して間もない頃からこうした支援につながっていたら、何か違う結果になっていたのだろうか…」そんな“タラレバ”を考えてしまうこともありました。
結局、病気になる前の状態に完全に回復することは叶わず、妻はこの作業所に約2年間通った後、退所することになりました。
2. 光をくれた人 ― 介護支援専門員Wさんとの出会い
そんな試行錯誤を繰り返す中で、私たち家族にとって、本当に大きな転機となる出会いがありました。それが、介護支援専門員(ケアマネジャー)のWさんとの出会いです。
Wさんは、特に精神障害を持つ方々の支援に長く携わってこられた、経験豊富なケアマネジャーさんでした。地域の福祉の現場で精力的に活動され、障害者支援の仕組みづくりにも関わってこられた方だと聞きました。2012年7月、私たちが初めて居宅介護サービス(ヘルパーさんの派遣など)を利用する際に、紹介されたのがWさんだったのです。
それまで関わってくださった支援者の方々も、もちろん一生懸命に対応してくださいましたが、Wさんはどこか違いました。妻本人の障害のことだけでなく、私たち家族全体を一つのチームのように捉え、どうすればみんなが少しでも楽になれるか、という視点で考えてくれたのです。
そして何より、「介護サービス計画(ケアプラン)は、介護を受けている本人や家族の希望を元に作るものですよ。介護者であるあなた自身の意見も、もっと言っていいんですよ」と教えてくれたのは、Wさんが初めてでした。(第2話で書いたように、それまでの私は制度を使うこと自体にどこか遠慮や難しさを感じていました)
就労継続支援B型事業所を退所した後、2015年の11月からは、Wさんが深く関わっていらっしゃる、身体障害を持つ方向けのデイサービスセンターに通所先を移すことになりました。
ある日の面談で、Wさんは私にこう話してくれました。
「奥さん、最近すごく良くなられていますよ。デイサービスでも、他の利用者さんの輪に自然に溶け込んで、とても生き生きと過ごされています。お昼ごはんの準備も、率先して手伝ってくださるんですよ」
その言葉を聞いた時、「ああ、妻は元通りにはなれなくても、ここなら安心して過ごせるのかもしれない」と、心から思えたのです。ずっと張り詰めていた肩の力が、ふっと抜けるような感覚でした。
また、そのデイサービスと連携している訪問介護事業所のヘルパーさんたちは、精神障害への理解も深く、安心して夕方の家事支援をお願いすることができました。これもWさんが繋いでくれた、大切な縁でした。
3. エピローグ:支え合いがくれた、前に進む力
Wさんとの出会いを通して、私は改めて気づかされました。介護保険制度や様々な支援サービスはもちろん大切だけれど、それを本当に活かすのは、「人」との繋がりなのだと。
誰かが見ていてくれる。気にかけてくれている。困った時に相談できる人がいる――。
ただそれだけで、介護という、時に孤独で先の見えない長い旅路の中で、「もう少し頑張ってみよう」「一人じゃないんだ」と、前に進む力が湧いてくるものなのですね。
Wさんやヘルパーの皆さん、そして(家出してしまったけれど、心のどこかでいつも気にかけていた)娘の存在が、当時の私にとってどれほど大きな心の支えになっていたことか…。
「介護は、決して一人で背負うものではない」
この実感が、ようやく私の固くなった心を、少しずつ解きほぐしてくれたように思います。
もしあなたが今、介護のことで一人悩み、疲れを感じているのなら…。この経験が、信頼できる誰かとの出会いを探す、小さなきっかけや道しるべになれたら嬉しいです。
関連記事
💡 一人で抱え込まないで――制度と専門家に頼ってみませんか?
信頼できるケアマネジャーさんとの出会いは、あなたの介護生活に確かな安心感をもたらしてくれるはずです。「どんなサービスが使えるの?」「誰に相談したらいいの?」と迷ったら、まずは公的な情報を調べてみましょう。
- ▶ 介護サービス情報公表システム(厚生労働省)
お住まいの地域の介護サービス事業所やケアマネジャーを探すことができます。 - ▶ 介護保険制度について(厚生労働省)
制度の基本的な仕組みを知ることができます。
あなたに必要な支援は、もうすでに用意されているかもしれません。諦めずに、情報を探し、相談する勇気を持つことが、状況を変える第一歩です。あなたとご家族の介護に、少しでも光が差し込みますように。
次回は、ケア体制が整っていく一方で、私自身の心の中に起きていた変化と、家族に起きたさらなる危機について、正直にお話ししたいと思います。
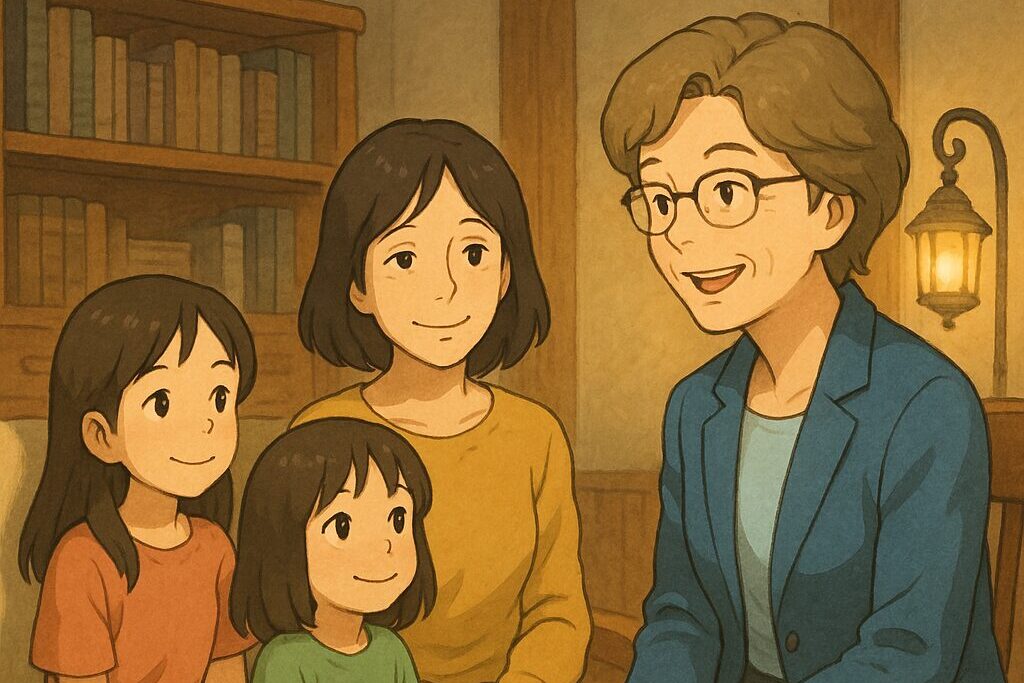



コメント